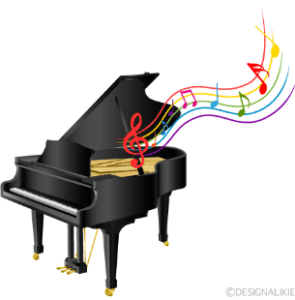🎹 世界一長いピアノ曲とは?⏳
ピアノ曲には短いものから超長時間にわたるものまでさまざまな作品がありますが、その中でも「世界一長いピアノ曲」として有名なものがあります。いったいどれほどの長さなのか、どんな曲なのかを詳しく見ていきましょう!
こんにちは、当ブログの管理人です。当ブログではアフィリエイト広告を
利用しております。それではごゆっくりとご覧ください。
🎼 1. 世界一長いピアノ曲とは?アメリカの作曲家エリック・サティの『ヴェクサシオン(Vexations)』 です。
「世界一長いピアノ曲」として知られているのは、アメリカの作曲家エリック・サティの『ヴェクサシオン(Vexations)』 です。
この曲は、たった1ページの短いフレーズを840回繰り返すという異色の作品で、演奏時間は通常18~24時間以上にも及びます。
🔹『ヴェクサシオン(Vexations)』の基本情報
- 作曲者:エリック・サティ(1866-1925)
- 作曲年:1893年頃(出版は1960年以降)
- 演奏時間:通常 18~24時間(演奏速度による)
- 演奏方法:短いフレーズを 840回 繰り返す
- 特徴:静かでミステリアスなメロディが続く
「Vexation」とは**「苦悩」や「苛立ち」**を意味する言葉で、この曲を繰り返し演奏し続けることが、演奏者にとっても聴衆にとっても一種の「試練」になると言われています。
⏳ 2. 『ヴェクサシオン』の長さと実際の演奏記録
ざうるす をチエック
🔹 世界的な演奏記録
この曲はその異様な長さゆえに、通常は複数のピアニストが交代しながら演奏します。
📌 有名な演奏記録
1️⃣ 1963年:初の公的な演奏(18時間40分)
- ジョン・ケージらのグループが初めて公開演奏
- 10人のピアニストが交代で演奏
2️⃣ 1970年代以降:各国でチャレンジ
- 世界各地の現代音楽イベントで挑戦が続く
3️⃣ 2009年:最長記録(24時間以上)
- カナダのピアニスト、ニコラス・ホーナーらが 24時間25分 かけて演奏
サティはこの作品を「840回弾け」と直接指示していたわけではなく、後世の研究者が「繰り返し回数」を発見し、それを実行するようになったのです。
🎹 3. 『ヴェクサシオン』の楽譜と演奏の特徴
楽譜はわずか1ページのみで、左手と右手が交互に動くシンプルなメロディーです。しかし、演奏者にとっては以下の点が試練となります。
🔹 『ヴェクサシオン』の演奏の難しさ
🕰 長時間の集中力維持が必要
→ 840回も同じフレーズを繰り返すため、演奏中に意識がぼんやりしやすい
🎼 単調なリズムが精神に影響
→ メロディの変化が少なく、長時間弾いていると感覚が麻痺する
🎹 指と手首に負担
→ シンプルな音形の繰り返しが筋肉に負担をかける
このため、演奏者の間では「精神と肉体の耐久レース」と呼ばれることもあります。
🏆 4. 他の長いピアノ曲
『ヴェクサシオン』以外にも長時間の演奏を必要とするピアノ曲があります。
🔹 有名な長いピアノ曲ランキング
| 曲名 | 作曲者 | 演奏時間 |
|---|---|---|
| ヴェクサシオン | エリック・サティ | 18~24時間以上 |
| ソナタ第7番 | カイホスルー・ソラブジ | 2時間以上 |
| グレインジャー編曲「ラモー組曲」 | パーシー・グレインジャー | 2時間30分以上 |
| ゴールドベルク変奏曲 | J.S.バッハ | 70~90分 |
| ハンマークラヴィーア・ソナタ | ベートーヴェン | 45~50分 |
「ヴェクサシオン」は圧倒的に長いですが、カイホスルー・ソラブジの作品なども「超大作」として知られています。
🎤 5. 『ヴェクサシオン』はなぜ作られたのか?
この曲の作曲背景は謎が多いですが、エリック・サティのユーモアと独特の作風が関係していると考えられています。
🔹 作曲の意図とは?
🌀 「反復による精神の変化」を体験させるため?
→ 840回繰り返すことで、聴く人の感覚が変わる実験だった可能性
📝 当時の音楽への風刺?
→ サティは伝統的なクラシック音楽に反発し、奇抜な作品を多く作った
🎭 個人的な心理状態を反映?
→ 作曲時期にサティは失恋を経験しており、心の苦悩を音楽で表現したとも言われる
実際に、この曲は「聴き続けることで意識が変容する」とも言われ、ある種の「トランス音楽」に近い要素も持っています。
「指が短くてもピアニストになれる?」
世界一長いピアノ曲『ヴェクサシオン』の魅力の
まとめ
✅ 演奏時間は驚異の18~24時間以上!
✅ 1ページの楽譜を840回繰り返すだけのシンプルな構造
✅ 精神的・肉体的に過酷な「音楽の耐久レース」
✅ サティのユーモアと実験精神が詰まった作品
✅ 過去には24時間以上の演奏記録も!
『ヴェクサシオン』は、普通のピアノ曲とは一線を画す「究極の耐久音楽」です。もし演奏会があれば、途中で休憩しながらでも一度体験してみると、その不思議な魅力に引き込まれるかもしれません!